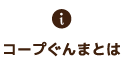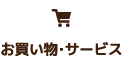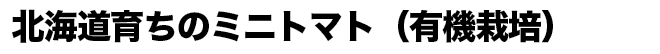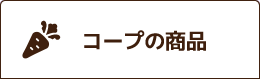おすすめ! コープの商品

生産者の佐伯昌彦さん(写真左)と息子の範彦さん。「土の力を最大限に使う有機栽培は、甘みだけではない、コクのあるミニトマトが育ちます」
そのままお皿に載せるだけで食卓が明るくなり、お弁当にも重宝するミニトマト。
洞爺湖が一望できる北海道の佐伯農園では、有機栽培のミニトマトが色付いています。
※取り扱いはコープデリ宅配のみ
暑さ対策で品質を維持
北海道の南西、美しい洞爺湖を臨む佐伯農園で赤く色付くのは、直径3センチほどのミニトマト。30年ほど前にミニトマト栽培を始めた3代目の佐伯昌彦さんは、「当時はミニトマトが市場に出始めたばかり。広まるかは半信半疑でしたが、切る手間がないのでホテルや学校給食の需要が伸び、やがてスーパーにも並ぶようになりました」と振り返ります。
当初は化学肥料を使用していましたが、「化学肥料は悪ではないけれど、使うと土が消耗して微生物が減り、連作障害が出やすくなる」と、有機栽培に挑戦。2000年に有機JAS認証を取得し、現在は1棟あたり約2.5トン収穫する農業用ハウス12棟で、ミニトマトを栽培しています。「多様な微生物が生息する土でこそ、私たちが目指す複雑な味わいの実が育ちます」
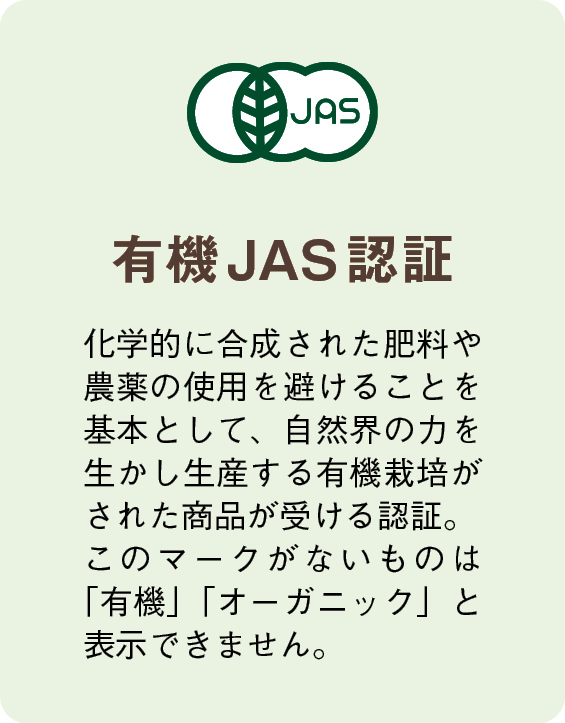
生産する上で最も重視しているのは、季節を問わず安定した品質と収穫量を維持すること。出荷期間が6月から10月末までと長く、今は北海道でも真夏は30度を超えます。日よけもかけますが、高温が続くと花粉が弱って受粉できなくなり、実割れも増えるため、今年は暑さにも強い品種に切り替えました。
「昨年この品種を育てている農家を見学し、これならと決めました。今のところ味も良く、順調に育っています」
「足るを知る」で持続可能な農業を実践
ミニトマトには、色つや、硬さ、熟度などさまざまな要素が求められます。「100点満点は無理でも、頑張って80点ぐらいは狙いたい。収穫量も同じ。肥料をたくさん与えればもっと多く採れるかもしれないけど、あまり欲を出さない方がいい。『足るを知る』というか、腹八分を良し、とするのが有機栽培なので」と昌彦さん。連作障害が起きにくく、畑を休ませる必要がないだけでもありがたいと言います。
「有機栽培では土の力を最大限に生かすので、実のおいしさに安定感があります。持続可能な生産は、農家の所得の安定につながり、ひいては消費者の利益につながります」と昌彦さんが言えば、息子で農園の中心的存在となりつつある4代目の範彦さんは、「日本全体の課題ですね。有機栽培が広がる仕掛け作りをしたい」と言います。「うちのミニトマトは、トマト本来の野生味があります。生命感あふれる味わいを楽しんでいただけたらうれしい。これからもこの地域で、土の力を生かした循環型農業に取り組んでいきます」
北海道・佐伯農園からお届けする大地の恵み。生産者限定の味わいを、ぜひお試しください!
北海道育ちのミニトマト(有機栽培)ができるまで
1. 播種・育苗・定植
長い期間、収穫・供給できるよう、1作目は1月下旬、2作目は2月下旬に種をまきます(写真A)。発芽したら育苗ポットに移し替え(B)、枝分かれしてきたら収穫量を多くするため主枝と脇芽1本以外を切って2本仕立てにします(C)。約60日間育てて最初の花が咲き始めたら畑に植え付けます(D)。

2. 誘引・芽かき・葉かき
4月中旬から支柱とひもを設置(写真E)。初めは支柱に沿って直立させ、2mほどに育ったら横に誘引します。ミニトマトは3枚の葉で1つの花房(F)が育つので、生育が盛んになる5月中旬以降は、実に栄養が行くよう脇芽や余計な葉をこまめに摘み取ります(G)。6月中旬には遮光ネットをかけ、3~4日おきに土中のチューブから水を与えます。

3. 収穫・選果・出荷
6月から収穫を始め、10月下旬まで続けます。最初に色付き始める1作目は、真っ赤に完熟したもの(写真H)を摘み取ります。暑さが本格化する7月中旬以降は少し早めに収穫(I)。作業前に採る実の色を確認し、朝5時から作業に取り掛かります。午後からは収穫と並行して選別。傷や割れがないか一つ一つ人が見て確認、出荷します。

4. 土作り
収穫が終わった11月中旬から半月ほどかけて、翌年のための準備をします。近隣の畜産農家から堆肥をもらい、そこに収穫後の葉や茎を細かく刻んで米ぬかと混ぜたものを加え、微生物による分解を促します。畑の土を掘り起こして自家堆肥を埋め込むと、翌年にはフカフカの有機質土壌に(写真J)。

【広報誌2025年8月号より】